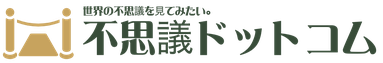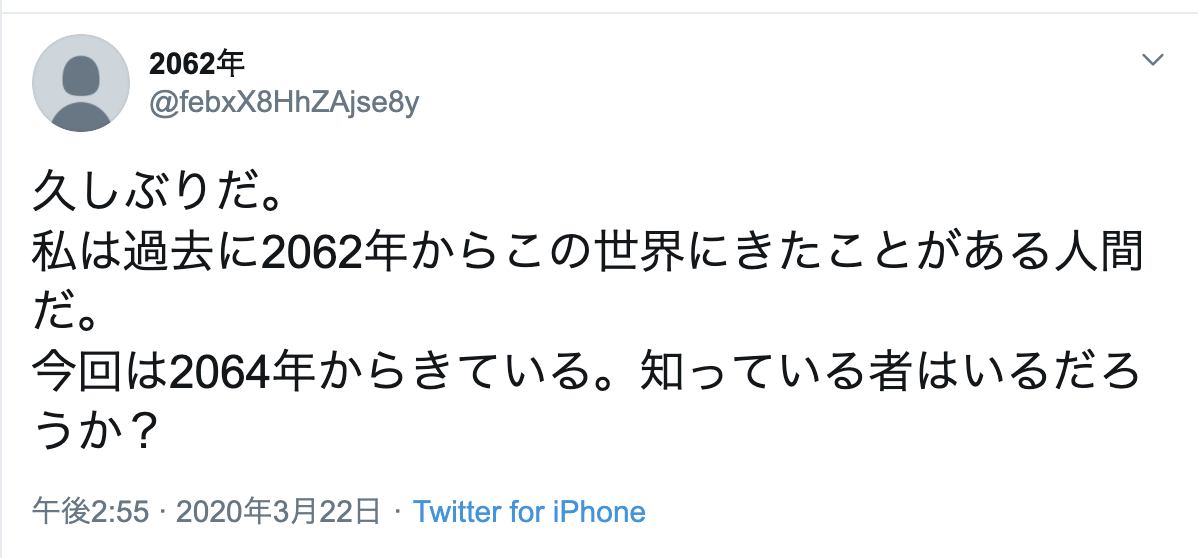時間を超えることは果たして可能なのか。
あの人とやり直したい、あの失敗を取り返したい、相場の動きを事前に知って大儲けしたいーー未来に過去に、自由自在に行き来できたらと誰しも一度は思ったことはあるだろう。
タイムマシンはいまだ開発されていないが、事故、あるいは偶然の結果、タイムトラベルとしか考えられない経験をしている人たちは何人もいる。
▼目次
迷い込んだ「500年前のパリ」
タイムトラベル先でマリー・アントワネットに出会う
空間も時間も超越し見た世界
1.迷い込んだ「500年前のパリ」
タイムトラベル体験を記録に残している人物は数多く存在する。
著名な博物学者として知られるイワン・T・サンダーソンは、その著書「続・事物」で、自身のパリ旅行について記している。
パリ旅行と言ってもただの旅行ではない。「500年前のパリ」である。しかも、その出来事はハイチで起こったというからややこしい。
当時、サンダーソン夫妻はハイチのポン・ブデという小さな村で暮らしていた。
ある日の夕方、夫妻と助手の3人は湖までドライブに行くことにした。
その道中、泥に車輪を取られてしまう。
なんとか脱出したが、そこから3人はクルマを諦め、歩くことにした。
突然、私は土の道から目を上に上げて、それに気がついた。道の両側にさまざまな形と大きさの三階建ての家々が、紛うことなくくっきりと並んでいる。
イワン・T・サンダーソン「続・事物」
明るい月の光を浴びて、それぞれの位置から影を地に投げている。
家はどれも道路にかぶさるような感じだ。
道路には舗装した様子はない。
比較的大きめの玉石が敷き詰めてある。
家々の感じは、英国ではエリザベス朝と思った。
しかし、私はそれがパリだと直感した!
カリブ諸島の小国であるハイチから遠く離れたフランス・パリに移動しただけでも驚きだが、事態はさらに複雑な様相を呈する。
一方にだけ勾配のある差し掛け屋根。切妻造りの柱廊廊下や仕切りのついた小さな窓。
窓から漏れる小さな明かりはろうそくの明かりのようだ。
サンダーソン氏だけではなく、妻も驚いた表情で周囲を見回している。
彼女の一言に、サンダーソン氏はさらなる衝撃を受ける。
「私たち、どうやって500年前のパリに来たのかしら?」
夫妻と助手の3人はその後、落ち着こうと縁石に腰を掛けてタバコに火をつけた。
ライターの火が目の前で消える。
それと同時に、15世紀のパリもふっとかき消えたという。
2.タイムトラベル先でマリー・アントワネットに出会う
「トリアノンの幽霊」と呼ばれるタイムトラベル事件も記録に残されている。
シャーロット・モバリーとエリナー・ジョーデンは、1901年にヴェルサイユ宮殿の庭園を散歩していたら、いつのまにか1789年のヴェルサイユにいた。
そこでふたりは、マリー・アントワネットや同時代の宮殿関係者の姿を見かけている。
この事件の特異な点は、体験者である女性ふたりとも、イングランドの名門学校であるオックスフォード・カレッジの学寮長を務める、「素性確かな」女性だったことだ。
タイムトラベルを体験した10年後、ふたりはこの経験を書籍にまとめたところ、大ヒットを記録している。


事件の概要はこうだ。
1901年の8月10日の午後、シャーロットとエリナーは、パリで何日かの観光旅行を楽しんだあと、ヴェルサイユ宮殿を見学することにした。
当時、ふたりはヴェルサイユ宮殿の歴史についても詳しくは知らず、たまたま手にした旅行案内書を頼りに宮殿を訪れている。
小トリアノン宮殿へ向かうことを決めたふたりは、まず木々が生い茂る小道を歩いて大トリアノン宮殿へとたどり着いた。
この建物を左折すると、芝生の生えた車寄せの道に出た。
ふたりは車寄せの道を横切って交差している細い小道へと入っていった。
このとき、シャーロットは細い道の曲がり角に建つ建物の窓から、ひとりの女性が白い布切れを振っているのを目にしている。
また、エリナーは細い道の脇に無人の農家が建っており、中には古いタイプの鋤が転がっていたと記録に残している。
その先には3本の分かれ道があった。
真ん中の道の前方に、ふたりの男性の姿が見えた。
彼女たちは歩み寄り、男性に道を訪ねると、その男性は「真っすぐ行け」と答えた。
シャーロットは後に「その男性は役人で、三角帽をかぶり、灰色がかった緑色の長いコートを着ていた」と書き残している。
同時にエリナーは、右手側にしっかりとした作りのコテージが建っており、建物の玄関の前に大人の女性と少女が立っていたことを記憶していた。
女性は少女に水差しを手渡そうとしており、「ふたりは絵画的なポーズを取っていたように見えた。ふたりが着ていたドレスは、その当時まったく見かけないスタイルのものだったので、特によく覚えている」と書き記している。
さらにその先の道でふたりは、天然痘のあばただらけの顔をした男性や、粗野な顔つきをした男性、絵画の中から飛び出したような紳士と出会っている。
小トリアノン宮殿にたどり着くと、シャーロットはスケッチをしている女性に出会う。
若くはないが美しい顔をしたその助成は、白い帽子をかぶり、古風でどこか変わったスタイルのドレスを着ていた。
後に、シャーロットはスウェーデンの画家、アドルフ・ウルリッヒ・ヴェルトミュラーが描いたマリー・アントワネットの肖像画を見た。
小トリアノン宮殿で見かけた女性は、この肖像画そっくりだった。

シャーロットとエリナーは、その後、建物の正面玄関から玄関広間に入り、行われていた結婚パーティーに参加している。
ふたりが前庭から外に出ると、小さい馬車が待機していた。
その馬車に乗ってヴェルサイユの中にあるホテルに戻っている。
この奇妙な体験から数カ月後、ふたりは互いの記憶を文章に書きとめ、トリトアンの歴史についての調査も開始した。
その結果、ふたりがトリアノンを訪れた日のちょうど109年前に当たる1792年8月10日にテュイルリー宮殿が襲撃され、スイス衛兵が虐殺された「8月10日事件」が起こっていたことが分かる。
事件以降、ふたりは何度も同じ場所を訪れたが、あの日に見た場所を見つけることはできなかった。
3.空間も時間も超越し見た世界
どちらの例も、日常を過ごしているうちに、ふと異世界に迷い込んだケースだ。
体験者が経験した世界が、本当に時空を超えた過去の世界だったのかはともかく、自らの意志ではなく、なんらかの偶然または意図せずに奇妙な経験をさせられている。
日本では、自らの意志で過去および未来へとタイムトラベルし、その経験を書籍に残している経験者がいる。
木内鶴彦が著した「生き方は星空が教えてくれる」(サンマーク出版刊)には、臨死体験中に体外離脱し、タイムトラベルに成功したと綴っている。
木内鶴彦は彗星捜索家として知られる。
航空自衛隊に勤務していた22歳のとき、上腸間膜動脈性十二指腸閉塞という世界でも珍しい難病で、一度は死亡を確認されるも30分後に蘇生している。
この体験によって「宇宙とはなにか、自分とはなにか」という問いを追求せざるを得なくなり、その疑問が天体観測に向かう原動力になったと後年語っている。
この空白の30分間の間、木内は体外離脱をしており、臨死体験を経験している。

何とかして自分が大丈夫だということを父に知らせようと、私は上半身を起こしました。
「生き方は星空が教えてくれる」木内鶴彦著
ところが父親の目線は起き上がった私を通り越し、ベッドの枕元を見ています。
おかしいなと思い振り向くと、そこには生命活動を停止した私の体が横たわっているではありませんか。
自分の声に反応しない父親のために、耳元で叫んでやろうと近くに歩み寄ると、目線がベッドに横たわる自分の体をとらえた。
体外離脱している木内が、父親の肉体に入り込み、父の目を通してものを見ていることに気がついたという。
父親の肉体にいてはいけないと肉体から出た木内は、看護師を呼びに部屋を出た、母親が戻ってきていないことに気がつく。
そう頭に浮かんだ瞬間、木内は公衆電話から電話を掛ける、母親のそばに立っていた。
姉に木内の死を知らせるために電話をしていた母親の会話を聞いているうちに、「兄にも自分が生きていることを知らせたい」と思った。
そう思った瞬間、今度は車を運転する兄の視点に切り替わったという。
そうです、私は考えるだけで空間を瞬時に移動することができるようになっていたのです。
「生き方は星空が教えてくれる」木内鶴彦著
戸惑いながらも「俺は大丈夫だから」といい残し、私は兄の体から出ました。
これだけでも十分異様な体験ではある。
しかし、木内の体験がさらに異常の度合いを増していくのはここからだ。
今の自分は肉体をもたない、いわば意識だけの存在だ。
「生き方は星空が教えてくれる」木内鶴彦著
もしかしたら意識だけの存在になる空間や時間の成約を受けなくなるのかもしれない。
もしそうならば、過去や未来にも行くこともできるかもしれない、そう考えたのです。
このとき、木内が思い出したのは6歳の夏の日の出来事だった。
兄弟で川に水遊びに行ったその日、幼い彼らは石がゴロゴロする、危険な斜面を降りていかなければならない状況に陥った。
足元に注意しながら川べりを目指して岩場を降りていたとき、上から「危ない!」という声が聞こえた。
驚いて視線を見上げると、大きな石が前を歩いていた姉の上に落ちようとしている。
慌てた6歳の木内は、前を歩く姉の背中をドンと強く押すと同時に、自分もその反動で後ろにひっくり返った。
先ほど目にした石が、ふたりの間をゴロゴロと転がり落ちていったのは、その瞬間だった。
姉は押された反動で足の親指の爪をはがしてしまい、木内はこっぴどく叱られた。
「危ない」という声が聞こえたと訴えても、だれもそんな声は聞いていない。
あくまでも、ふざけた木内が姉の背中を押したと解釈されていた。
幼い木内は、その日の悔しい思いをずっと引きずっていたという。
あの夏の日に行きたいーーーそう思った瞬間、私は幼い自分と姉の姿を上から見下ろしていました。
「生き方は星空が教えてくれる」木内鶴彦著
幼い日の記憶を頼りに私は声のした方へ行ってみました。
(中略)
しだいに、あの瞬間が近づいてきました。
石が転げ落ち、姉がまさにその場所に足を乗せようとしたとき、私は思わず叫んでしまったのです。
「危ない!」
幼い自分が私のほうをパッと向き、姉の背中を押しました。
ーーあのときの声の主は自分だったのです。
この体験をした臨死体験中の木内は、一度病室へと戻る。
混乱の真っ最中ではあったものの、少し冷静さを取り戻すと、「過去に行けたのだから、未来へ行くこともできるかもしれない」と考えたという。
(前略)
「証言・臨死体験」立花隆著
『過去にも行けたし、現在の遠く離れた場所にも行けた。これは、自分の動きが時間にも空間にも成約されないということなのだから、もしかしたら未来にも行けるんではないだろうか』。
それまで、どこかに行ってみたいと思うとき、自分がどこそこに行きたいと頭の中で念じるだけでそこに行けたので、今度も、ただ、未来に行ってみたいと念じてみました。
(中略)
大きな畳の部屋で、沢山の人を前にして、ぼくが星の話なんかをしているところでした。僕は灰色っぽい服を着ていました。
目にしている光景が未来のものならば、自分はいずれ生き返る。そう思ったら嬉しかったと木内は語っている。
実際、木内はその後に息を吹き返し、日常生活を送れるほどにまで回復する。
そして。
そのとき見たものが本当に未来で起きたんです。
「証言・臨死体験」立花隆著
それが去年高野山であった京都フォーラムの会だったんです。
(中略)
襖を開けると、向こうの部屋がL字型に連結していました。
そしてそこに、あのときみた朱色の絵がかかっていたんです。『えーっ』と思いましたよ。
演壇から、聴衆から、みんなの前で話しているぼくの様子から、みんなあのとき見た通りの情景になったわけです。
「証言・臨死体験」におけるインタビュアーの立花隆は、「デジャ・ヴュではないのか」と質問するが、木内が臨死体験中に未来の光景として目にした風景に、再びであったのは19年後のことだった。
「突然19年前のことを思い出したわけではない。ずっとその風景を覚えていたのだから、自分の心の中でははっきりしている」と木内は答えている。
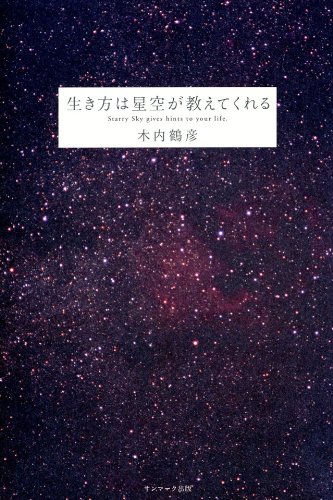
自身が体験したタイムトラベルが詳細に記述されている